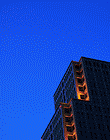K20D ダイナミックレンジ拡大機能を考える #4

Eze にて - Pentax K20D, smc Pentax FA77mmF1.8 Limited
エズは “鷲の巣村” といわれる集落の 1 つだ。その名のとおり、麓から見ると断崖に張り付いているようだ。村一番の高さのシャトーの頂上からは、地中海を文字通り見下ろすことができる。
ヴィルフランシュシュルメールとは対照的に、あまり生活の匂いはしない。
きれいな観光地、だ。
・・・
K20D の A/D 変換 (アナログの光量をデジタルの数値に置き換える) は 14 bit。一方、K20D の raw フォーマットは 12 bit。つまり、A/D 変換した時点では、raw フォーマットより 4 倍細かいグラデーションを持っていることになる。
理論上、raw に保存する際に一部を 4 倍に引き伸ばしてもトーンジャンプはない、ということになる。
それなら、と、実際に設定された ISO 感度より 1 段暗い感度で取り込んで白飛びを回避し (白飛びだけはどうしようもないので)、raw に保存するときにトーンカーブの両端を変えずに中心を全体的に明るいほうにシフトしてダイナミックレンジが広げよう、っていうのがソフトウェア的ダイナミックレンジ拡大機能。(もちろん、シャドー部のノイズの少ないことが条件ですけどね。)
でも、ここでちょっと待てよ、と思うでしょ?
だって、12bit/c raw で撮影して最終的に 8 bit/c の jpeg に落とすなら、その時点で 16 倍も余裕があるんだから、カメラに勝手にやられるなら自分でやるよ、って。
それ、正解。
12bit/c の raw から 8bit/c の jpeg に落とすなら、ソフトウェア的なダイナミックレンジ拡大が必要になる場合はほとんどない。
ただ、最終が 16bit/c の tiff に落として紙焼きする場合は別。この場合、12bit/c の raw のまま tiff に落としてもデータ的にはトーンジャンプするわけで。
つまり、ISO100 をどうしても使用しなければいけない場合以外は、raw で撮るとしてもダイナミックレンジ拡大機能を使っている方が有利・・・と言いたいところだけど、使ってみるとそうとは言い切れないんだよね・・・ (次回に続く)
・・・
** 皆さんの日々の“応援ポチ”が僕のモチベーションの源泉です。
よろしくお願いします (u_u) →に投票
・・・





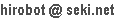 まで
まで